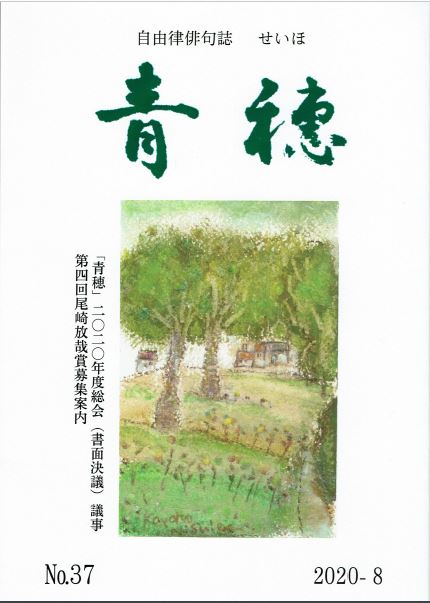青穂38号が発行されました
お知らせ
2020年11月8日日曜日
青穂38号が発行されました
2020年11月1日日曜日
ハイクノミカタ
2020年10月16日金曜日
宗左近句抄
響灘 潮が満ちれば必ず発熱する
帆柱山 ゆらり夕焼け 空の沖
目を開けぬ土筆の聴いている風の青
自殺願望とは他殺願望 乱れ太鼓の大花火
わたし下地っ子 蒲公英の羽根みな毟る
重かねえ 夕顔 わたしはわたしの肉なのね
火の海のなかの竜巻き おれの死体おれから噴き出して
熊蟬(くまんぜみ) 戦わない鏡を叩き割る
明日も敗戦日 真深にかぶった夜明けず
空の青 海の青 地上に棲めぬものばかり
冷凍の鱈仔が鱈たちになるだろう日のオーロラの空
虫すべて食べられ終えてから目を閉じる
空の黒い囚人服 干葡萄
きみの朧夜に舌の尖(さき)の灯を移す
萬緑の 少年の産む大卵(おおたまご)
死んで背泳ぎ 蛙の水掻きの空の白
蛤の太腿伸す月の梅雨
骨壺のなかの炎天 灰の花
蝸牛 夢の螺旋を這っていて
大空襲 美しさとは人を光にすることでした
骨を拾った箸だから焼くほかはない
枯山水 鬼面をとれば 顔あって
蛍二匹 光として 闇として
腐って行く桜桃のなかの大満月
※下地っ子 芸者見習い 作者の従妹のこと
宗左近は詩人、俳人、美術評論家。関東大震災で、一緒に逃げた母親を眼前で死なせてしまうという壮絶な過去を持つ。「炎える母」というタイトルの詩は、この経験に基づいたもの。近藤洋太「詩の戦後」によると、死の直前の言葉として、こう書かれている。
「カミサマの馬鹿野郎。プラネットに地球なんか生みやがって、だから俺は産まれてこなきゃならなかったんだ、メイワクだっ」
これらの一行作品を、作者は、俳句以前現代詩以前(意味的には「未満・以下・劣る」ということではなく、技法的にそれらとは別のもの、と私は解釈しています。)の「中句」と呼んでいたようです。個人的にこの作風はとても参考にしています。
宗左近の名を冠した俳句の賞があったのですが、残念ながら今はありません。
おおげさな物言いかもしれませんが、文化を下支えしているのは、案外手弁当・小規模なものが多く、好きなもの残したいものは「個人」が積極的にかかわっていかないと「大衆の嗜好」の影に隠れて消えてしまうものだと分かったのは、大人になってからのことでした。
(文:久坂夕爾)
2020年10月4日日曜日
同人の句より
気になる句があれば幸いです。
コメントは的外れ・不愉快かもしれませんが(句を読んでもらうきっかけにしたいだけですので)同人の方はご勘弁を。
尾崎放哉賞募集中です
第4回尾崎放哉賞。締め切りは11月30日です。
応募は2句一組。応募用紙は、下記サイトからダウンロードできます。
第4回尾崎放哉賞
2020年9月22日火曜日
まさかジープで来るとは
日常の微細な場面の「心理的落差」を掬い取った自由律俳句。
「カキフライが無いなら来なかった」「まさかジープで来るとは」
(せきしろ、又吉直樹共著)で知られる自由律の作風は現在人気があるようで、
せきしろ氏は、こういう公募もやっているようです。
https://www.koubo.co.jp/reading/rensai/oubo/haiku/jiyuritsu42.html
軽さや、心理に絞ったことの狭さを感じてしまうからか、
消費されやすいと思ってしまうというか、
単なる「そういうことあるよね」という共感ネタになりやすいので、
私自身は特に惹かれないのですが、
場のキャッチボールは成立しやすく面白いですよね。
こういうものもある、ということで。
日常の非常に小さな場面を確実にとらえうる眼を鍛える、
という点ではいいと思います。
(文:久坂夕爾)
2020年8月30日日曜日
青穂37号よりお知らせなど
2020年8月10日月曜日
青穂37号が発行されました
2020年7月18日土曜日
尾崎放哉賞募集始まっています
11月30日締め切りで応募は2句一組。
応募用紙は、下記サイトからダウンロードできます。
twitterでは先行してお知らせしています。
こちらでのお知らせが遅れてしまいました。
第4回尾崎放哉賞
こちらもうっかりお知らせが遅れてしまって、
中の人には申し訳ないですが、
「青穂」のtwitterが開設されています。
フォローよろしくお願いします。
ブログ更新時にもツイートされますので。
https://twitter.com/seihojiyuritsu
放哉の句から一句。
入れものが無い両手で受ける
有名なこの句の原型のような句があります。
両手をいれものにして木の実をもらう
「もらう」が「受ける」に、
1センテンスが2つのセンテンスに。
私には、
自意識をそぎ落して、行為や事実の輪郭だけ描くようにしたと思うのです。
(文:久坂夕爾)
2020年6月28日日曜日
金子兜太・田村隆一の対談
金子兜太・田村隆一の対談の中で、興味のひかれた部分を。
(田村)
ただ、俳句の持っている僕の言うほんとうの意味での即興性というのは、「私」をこえたところにあるんだから。「私」をこえた表現というものを支える俳句の知的な凄みというのかな。そういったものがもっとゆるやかな広がりを持てれば、僕はいいとおもうんですよ。
(ー略ー)
(金子)
僕は日常性を強調しているんです。……そうなんですよ、たしかに。そこを土台に自在に飛翔すれば、言霊とか、幻想とか、想像の世界とか、そういうものを迎え入れることもできる。
(田村)
言葉自体が大きな喩ですからね。言葉というのは比喩なんですよ。(略)季語はその大きな喩のなかの喩を機能させるための喩であって、要するに僕たちは暗喩をいろいろ使う、それはいろんな形で使う、詩人というものは。しかし、実はただ暗喩を使うために使っているんじゃなくて、大いなる直喩を発見したいために暗喩を使っているんだ、と言ったことがあるんです。
(ー略ー)
(金子)
それは同感だな。若い連中は言語論の入門書なんかを読んでその受け売りをやるんだな。言葉の一人歩きだけやるんですよ。
金子兜太のほうが聞き役に回ることが多い、という印象を受けましたが、
これは座談会ですので、たぶん編集の仕方によるのでしょう。
「季語は喩である」「季語は固定化されたルールではなく、社会や地域や時代の変化によって変わっていくもので、俳句の世界を広げる入口のようなもの」という部分は、やはりそうですよね、という感想。
荻原井泉水の「詩と人生 自然と自己と自由と」に、
芭蕉の「物と我と二つになりて其情誠にいたらず、私意のなす作意なり」に関しての記述がありますが、上記座談会でも「物」と「我」との関係について話題に上っていました。
厳密に本意を追うと矛盾や飛躍に見えるところもあるのですが、思っていることがフラットに出て来るところが座談会の面白さですね。
(文:久坂夕爾)
2020年6月12日金曜日
2020年5月24日日曜日
第3回尾崎放哉賞発表
2020年5月10日日曜日
2020年4月25日土曜日
昼顔
ヒルガオ立ち枯れ触れてはならぬ 小山貴子
昼顔順列 吉原幸子
昼顔は女だ
わたしは女だ
女は昼顔だ
昼顔はあなただ
あなたは女だ
わたしは昼顔だ
女はあなただ
あなたは昼顔だ
女はわたしだ
昼顔はわたしだ
わたしはあなただ
あなたはわたしだ
(以下「NOTE」より)
この時期、私は変った。かつて「詩は排泄だ」とうそぶいてゐた私も、やっと世界をそのまま呑み下し、完全消化することを覚えた。私の胃が健康になったのか、それとも食べすぎなくなったのか。――徐々に、ことばは私から遠ざかりつつある。私はそれを悲しんでゐない。
詩集「昼顔」所収
(文:久坂夕爾)